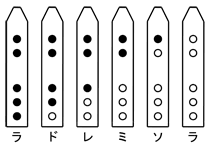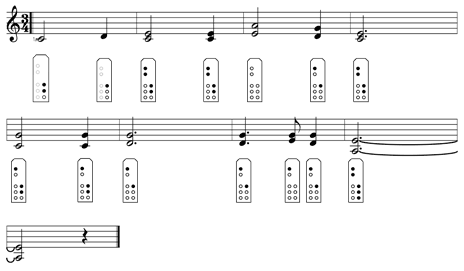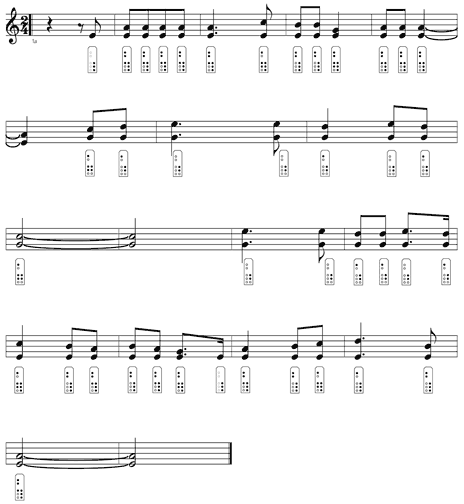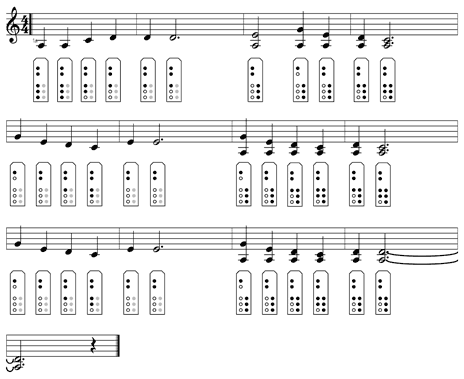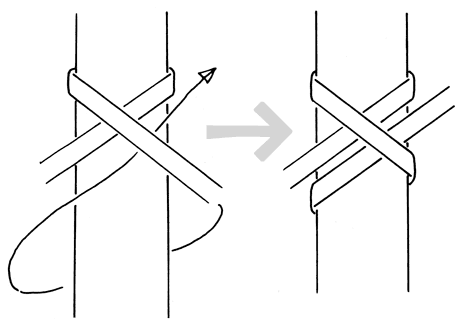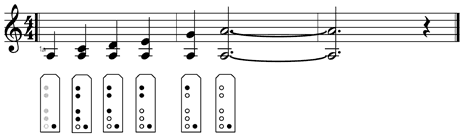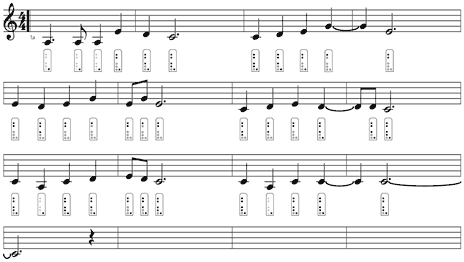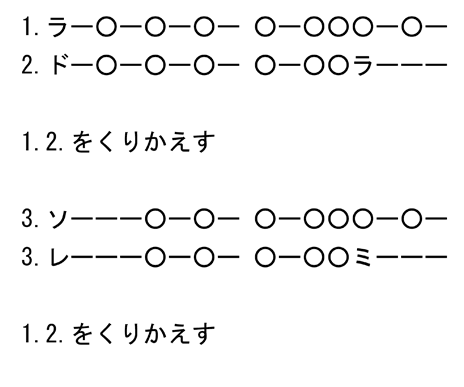インディアンフルートは古くて新しい楽器
絶滅寸前だったインディアンフルートが北アメリカでリバイバルしたのは20世紀のほんとうに終わりごろです。指穴が5つだとか6つだとかマイナー五音階だとか、今のインディアンフルートの形は、それから10数年の間にばたばた決まったことです。だからインディアンフルートは生まれかわった新しい楽器ともいえるでしょう。誰でも鳴らせる、フィーリングで吹いても曲に聞こえるインディアンフルートは、北アメリカインディアンの哲学・ライフスタイルとともに全世界に広まりました。
アステカの土笛をヒントに


2本のインディアンフルートを束ねていっしょに吹くこと、ドローンフルートを誰が最初に発明したのかわかりません。中央アメリカのアステカ・マヤの遺品―2つの音が出る土笛―をヒントにした、というのがおおかたの定説です。
ドローフルートを実際に手にとってみて実感するのは、これを製作するには高度な西洋の工作機械が必要だということです。21世紀の工業国USAだから生産可能な笛であって、北アメリカインディアンのネイティブな技術ではとても作れない。そんな代物をインディアンフルートと呼んでいいのか、という議論はありますが、吹いてみるとこれがなんともインディアンな音がします。

インディアンフルートが趣味の人なら「一本くらい持っておきたいな」とあこがれる笛です。
ドローンからダブルへ
通常のドローフルートでは伴奏管に指穴がありません。伴奏管はいつも同じ低音―ドローン―を鳴らします。演奏方法はふつうのインディアンフルートとまったく同じで、簡単に一人合奏が楽しめるので、これはこれで人気です。
しかし同じ音ばかりでは変わり映えがない、もっといろんな和音の組みあわせを楽しみたいと、伴奏管にも指穴をあけたタイプが考案されました。この伴奏管に指穴をあけたタイプを区別して、当サイトでは”ダブルフルート”と呼んでいます。


- ドローンフルート…伴奏管に指穴がない。いつも同じ音を鳴らす。
- ダブルフルート…伴奏管に1つ以上の指穴がある。伴奏の音を変えることができる。
伴奏管の指穴位置はまだスタンダードがなく、いろいろな工房で試行錯誤の途中です。ここで説明しているダブルフルートは、伴奏管に3つの指穴が開いているタイプです。

» ダブルフルートを吹いてみた