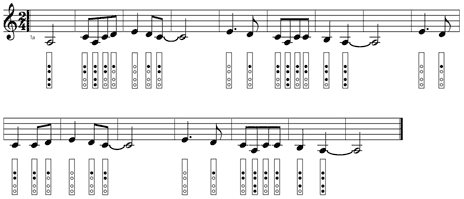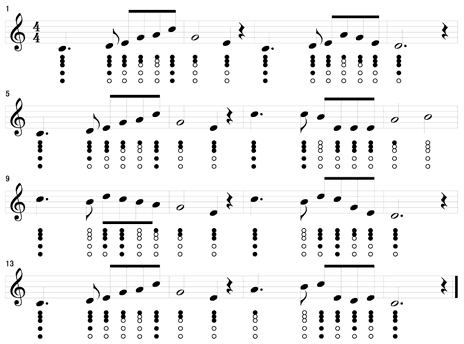1人で合奏ができるダブル・インディアンフルートです。» カラオケ音源を用意しました、使ってください。
【ニコニコ動画】2音インディアンフルート『聖母マリアの七つの喜び』
曲について
『聖母マリアの七つの喜び』は古い歌なので、メロディーの異なるバージョンが存在します。私が初めて聞いたのはアイルランドのドネゴール郡に伝わるバージョンでした。静かで神聖な雰囲気の曲で、一発で気に入りました。しかしながら世間で知られているのはむしろ、スィング気味の脳天気な曲調のバージョンです。それを知っている人は(なんでこんな曲をインディアンフルートで吹くのだろう?)と敬遠するかもしれません……今回は非常に損な選曲をしてしまいました。
七つの喜び、ということはご明察のとおり、1番から7番まで歌があります。とはいえ笛で同じフレーズを7回もくりかえすとさすがに飽きるでしょうから、4番までしか演奏してません。
楽器について
アステカ族の末裔、ナッシュ・タベワが製作したダブル・インディアンフルートで演奏しています。
インディアンフルートは北米インディアンに伝わる笛です。ダブル・インディアンフルートはそれの改造版で、2本の笛を1本に束ねた笛です。同時に2つの音を出せるので1人で合奏ができます。石器・土器しかなかった昔のインディアンたちがこんなゴツい笛を吹いていたはずもない。ダブル・インディアンフルートは高い工業技術によってのみ製作可能な、20世紀末に生まれた新しい楽器です。
……なんて堅苦しいことを言わずに、吹いてみると意外にこれがインディアンな雰囲気なのですよ。インディアンフルートを嗜む人なら(一本は欲しいな)と憧れる楽器です。
演奏方法について
『聖母マリアの七つの喜び』の運指は演奏動画に載せています。一時停止しながらご確認ください。
左側の管は、6つの指穴ぜんぶを使います。レザーバンドは外してください。右手側の管は、下の2つの指穴しか使いません。3つあるうちのいちばん上の穴は、耳栓で塞ぎます。
動画を見てのとおり、右手で左右両側の管の指穴をいっしょに押さえる箇所があります。なので同じダブル・インディアンフルートでも、枝切りハサミのようにAの形になっているタイプでは演奏できません。
『聖母マリアの七つの喜び』の曲自体は、短くて覚えやすい易しい曲です。ふつうのインディアンフルートで吹いてもいい感じですよ。
作品について
製作途中に(なんだかヴァンゲリスみたい……)と意識した瞬間、変なスイッチが入ってしまって「ヴァンゲリスならこんな音を使うよね」「ここはこんな感じにするよね」とますますヴァンゲリスっぽくなってしまいました。
おかげで曲のインパクトを表現する新しい方法を学びました。
ユニゾンも、実は今回やったのが初めてです。
このへんの知識は、たくさんの楽器を使ってシンフォニックな表現をするのに重要な気がします。次回作でも引きつづき研究してみます。
製作ノートは製作中に書くもの
この文章は伴奏が出来上がった段階で、ファミレスで食後のコーヒーを飲みながら書きとめたものです。今までは作品に関する説明などは、演奏動画をネットに投函した後になって考えていました。しかしそれだと気持ちはもう済んでしまった事になっているので、どうにも頭が回りませんでした。このように、製作工程の途中途中で気づいたことを書きとめておけばよかったのです。